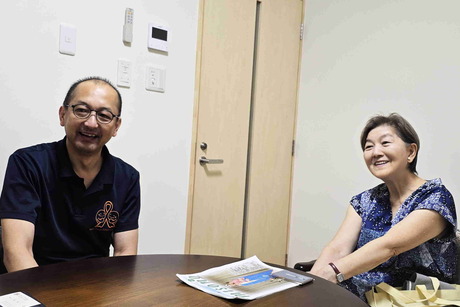- HOME
- 【取組紹介Vol.14】 子どもたちの暮らしを地域とともに見守る「社会福祉法人みその児童福祉会 高知支部」の取り組み【後編】
今回は「社会福祉法人みその児童福祉会 高知支部(高知市)」のインタビュー後編です。高知支部では、複合的な支援機能を備えた施設の運営を通じて、子どもや保護者に寄り添った支援を行っています。地域に開かれた取り組みや今後の展望について、支部長の谷本さんと高知支部が運営する児童養護施設「高知聖園天使園」の副園長・坂本さんにお話を伺いました。
※前編はこちらからご覧いただけます。
高知支部の取り組みについて語る谷本支部長と坂本副園長
===
社会福祉法人みその児童福祉会高知支部
岡山県に本部を置く社会福祉法人みその児童福祉会の高知支部は、2008(平成20)年に社会福祉法人聖心の布教姉妹会から福祉事業を引き継ぎ、運営を開始しました。児童養護施設、乳児院、児童家庭支援センターなどを展開し、子どもたちの暮らしを支えるとともに、保護者や地域との関わりにも力を注いでいます。
“地域社会のニーズを的確に把握し、速やかに対応する”をモットーに、子どもと家庭、地域があたたかくつながる関係づくりを進めています。
===
「高知家地域共生社会」では、介護や子育て・就労困難者のサポートなど、分野を超えた包括的な支援体制の整備を進めています。その実現に向けて取り組みを行う県内各地の実践事例をご紹介します。
見えにくい困りごとに寄り添う支援体制
「子ども宅食応援団」イメージ(提供:社会福祉法人みその児童福祉会)
-みその児童福祉会 高知支部で行われている「子ども宅食応援団」について教えてください。
谷本さん:この事業は、地域で生活する子どもたちの家庭に食事や衣類など、必要なものを聞き取って届けるという取り組みで、高知市からの補助や企業からの寄付により実施しています。子どもたちの生活環境は家庭によって大きく異なり、経済的な問題だけでなく、親御さんの病気や育児疲れなど、複雑な課題を抱えているケースも少なくありません。
-食だけでなく、生活に必要なもの全般を支援されているのですね。対象となるご家庭とは、どのように接点を持たれるのでしょうか。
谷本さん:地域の保健師さんやスクールソーシャルワーカーさんが家庭訪問をした際の情報をもとに、必要なものを用意してお渡しするようにしています。朝食を食べてこない子がいると聞いたら、校長室や保健室にストックの食材を用意して渡すこともありますね。
-そこから見えてきた、昨今の課題などはあるのでしょうか。
谷本さん:親の状況次第で、子どもが困難な状況になってしまうことがあります。親御さんに元気になってもらうことが大切です。親御さんが病院に行けていない状況なら受診を勧めたり、不登校のお子さんが学校に少しでも行きたくなるように、うちの職員がきっかけづくりをしたりしています。
実際に、学校に行けるようになった子に対しては、その後の学校生活をサポートすることもあります。子育てには親支援の体制が必要だと思っています。全ての子どもの健全育成のために地域全体で支援という気持ちでやっていますね。
物資支援だけで終わってしまうと、そのご家庭は変化しません。何に困っていて、何を改善すれば少しでも変化を期待できるのか。その変化によって、子どもがもう少しいい状態に変わることができるよう、サポートしています。
-地道なコミュニケーションの積み重ねの中で、信頼関係を築かれているのですね。
谷本さん:訪問回数を重ねる、繰り返しの中で関係性や信頼が築かれていくように思います。はじめは、訪問してもドアを開けてもらえないこともあります。しかし、少しずつお顔を合わせられる機会を増やして、会話のなかから何に困っているか、改善に向かう糸口を見つけます。
センターの職員だけですべてできるわけではないので、保健師さんやスクールソーシャルワーカーさん、行政と連携しながら進めています。
また、取り組みの一部は企業からの寄付により実施することができています。この取り組みにご賛同いただける場合は、お問い合わせをいただければと思います。
【お問い合わせ】
児童家庭支援センター高知ふれんど(〒780-0062高知市新本町1丁目7-30)
TEL:088-803-5550FAX:088-803-5770E-mailkochi-friend@crest.ocn.ne.jp
-「子ども宅食応援団」の取り組みはアウトリーチの役割も担っているのですね。
子どもたちの未来を見据えて
-今後は、どのようなことに取り組もうと考えられているのでしょうか。
谷本さん:取り組みたいことはたくさんあります。まずは、「子ども宅食応援団」をさらに充実させ、高知県内のより多くの家庭をサポートできたら、と考えています。
そして、施設周辺の地域は高齢化が進み、町内の活動が減っているので、清掃活動や防災活動などを通して地域とのつながりを増やしていきたいです。建て替え前に行っていた夏祭りを復活させたいとか、いろいろな構想がありますよ。
坂本さん:大きな建物になったことで、少し入りにくい印象になってしまっているかもしれませんが、複合棟は地域の災害時の避難場所でもあります。
シスターがいた時代から、地域の方とつながりを持たせてもらってきました。それが途切れないように、地域の方々と一緒にいろいろな取り組みを進めていきたいです。
防災をもっと身近に感じる機会に
「シェイクアウト訓練」中の子どもたち
-2025(令和7)年6月に、高知市地域防災推進課「あなたに届け隊 出前講座」が、みその児童福祉会 高知支部で実施されましたので取材をさせていただきました。これまでも施設内では毎月避難訓練を行っていますが、今回は外部講師を招くことで、子どもたちにとって新鮮で学びの多い時間となったようです。
講座ではまず、地震の恐ろしさや命を守る行動について、動画を交えてわかりやすく紹介されました。その後は、クイズ形式で知識を確認しながら、地震に備える防災訓練「シェイクアウト訓練」も実施。子どもたちは楽しみながらも真剣な表情で取り組み、小さなお子さんも集中して耳を傾けていました。
また、地域にあるホームのひとつでは、この出前講座を避難訓練と組み合わせ、リュックサックやヘルメットを身につけて、歩いて避難場所(複合棟)に向かう取り組みもされていました。防災をより「自分ごと」として考えるきっかけになったのではないでしょうか。
今後も外部講師を招いたり、地域のなかで防災教育を行ったり、さまざまな構想を練られているそうです。
-子どもたちの安心できる暮らしを支えるだけでなく、地域とともに歩もうとする想いが、みその児童福祉会 高知支部の取り組みのあらゆる場面から伝わってきました。
困難な状況は目に見えにくいものですが、一人でも多くの子どもたちが、少しずつでも前に進める環境が広がっていくことを願っています。
谷本さん、坂本さん、温かく前向きなお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
なお、こうした活動を継続するためには、皆さまのご理解とご協力が欠かせません。支援のかたちはさまざまで、寄付による応援はもちろん、見守っていただくことや、情報を周囲に広めていただくことも大きな力となります。
法人のSNSでも日々の取り組みを積極的に発信されていますので、ご関心のある方はぜひフォローしてみてください。
記事執筆:是永 裕子
▶ 関連記事はこちら → [取り組み記事一覧へ]